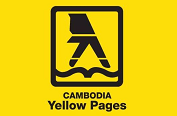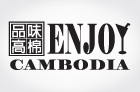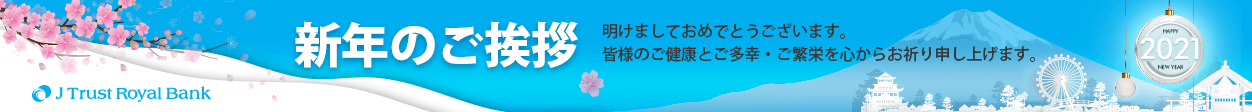

高層ビルや高級コンドミニアムが次々と建設され大手小売や飲食チェーンの進出も相次ぐなど、カンボジアの高度経済成長を象徴する首都プノンペンはその要望も一変した。一方、首都近郊から少し離れればすぐに見渡す限りの田園風景が今も広がっている。首都の眺めの急激な変化とは対照的に、どこまでも続く昔ながらの原風景だが、そこでの農業の営みには大きな変革が起き始めている。首都経済からは見えてこないカンボジア農業変革の潮流を追う。
一方、コメの国際マーケットの傾向は追い風とは言い難い。世界が来るべき食糧危機へのホラーストーリーに沸いた約10年前、コメ取引関係者はそのブームに乗るかのようなコメ価格の急騰に沸いていた。コメ国際流通価格の代表指標である「タイ白米100%ランクB」の輸出価格(FOB)は、2006年頃は1トンあたり300米ドル前半を推移していたが、2007年から急騰し始め、2008年4月は1トンあたり1000米ドルを突破した。
危機感を抱いた各国は自国生産のコメ輸出に規制を開始し、カンボジアも200トン以上のコメ輸出の際には許可を必要とする規制を敷いた。ピーク時からは落ち着いたものの依然コメ価格が高止まりを続ける中の2010年5月、他国に先駆けてカンボジアがその輸出規制を撤廃し、フンセン首相は同年8月にコメ産業育成のための包括的国策として「ライス・ポリシー」を打ち出す。灌漑・輸送等の農業インフラや関連金融インフラなど農業改革に必要な幅広いインフラ整備を促進し、当時のコメ正規輸出量の5倍となる100万トン輸出を2015年までに達成すると打ち出し、この「ライス・ポリシー」を経済復興フェーズに突入したカンボジア国家再建の柱の一つとなる重要指針と位置付けた。
高止まりするコメ国際価格に期待を寄せ、コメを「ホワイトゴールド」とまで評し戦略輸出物資に担ぎ上げようとしたカンボジア政府だったが、事は思うようには進まなかった。この「ライス・ポリシー」に至る初動となったカンボジアのコメ禁輸解除は、当時の英紙フィナンシャルタイムスに、「カンボジアのコメ禁輸解除に初名乗り、コメ国際相場に緩和の兆し」として取り上げられ(2010年5月27日、2面)、事実その後コメ相場は下落傾向に傾く。2010年後半に1トンあたり500米ドルを割り込んだコメ国際価格は、その後600米ドル代を回復するものの2013年後半には再び500ドルを大きく割り込んだ。
2015年にコメ100万トン輸出を掲げた「ライス・ポリシー」だったがコメ国際相場の逆風や インフラ整備の遅れ等からこちらも思うように進まず、結果目標の半分程度の輸出量で2015年は終了。当社も当時事業としてカンボジアのコメを欧州ポーランドに輸出していたが、500ドルを割り込みどんどん下がっていくコメ相場と相対する厳しさを今でも鮮明に記憶している。あの状況で事業者がコメ輸出を促進できるわけがなく、「ライス・ポリシー」は当時からほぼ形骸化していたと言える。
その後、コメ国際価格は2016年には300ドル代まで落ち込みを見せながら、本稿執筆現在は450ドル前後まで何とか持ち返している現状である。
コメの国際マーケットを見るにその状況はあまり芳しいとは言えない中、筆者がカンボジア農業現場で見る限り現地農家は淡々と稲作を続け、コメ国際価格の騰落に良くも悪くも過度に大きな影響を受けているようには見えない。その理由の一つはコメが基本「地産地消」の農作物であるからだ。
米国農務省の発表によると、世界のコメの生産量は年間約4.8億トンでその約9割がアジアで生産されている。その特徴としてあげられるのは、世界有数の生産量を有する穀物でありながらその貿易量が少ない事だ。
世界で輸出入されるコメの量は全体生産量の9%ほどに過ぎず、同じく大きな生産量を誇る小麦(22%)や大豆(40%)に比べてもかなり低い水準だ。コメの大量生産国としては 中国(約1.4億トン)とインド(約1億トン)が突出しているが、人口も巨大な中国はむしろ輸入量が輸出量を上回っており、またインドは最近ようやくコメ輸出トップに躍り出たが総額1000万トン程度。コメ輸出国として名高いタイやベトナムがそれに続くが、両国ともコメの生産量は2000万~3000万トン程なのに対 し、国内人口がインドの10分の1にも満たないため余剰のコメを輸出に回すことができる。カンボジアを含む東南アジア諸国がコメ輸出大国となる理由は、メコン川等の大きな河川や肥沃な大地などの土壌条件に恵まれ人口に対してコメが相対的に大量に生産されるため、内国民の食を十分に満たしてもなお余剰が生まれるからだ。
カンボジア国内を見てもここ10年のコメ国際価格の騰落幅に比べれば国内価格は安定しており(当然国際価格につられて長期的にダウントレンドではあるが)、かつその価格に合わせて生産調整をする必要があるような大規模農家はほぼ存在しないため、カンボジア農家は毎年変わらず淡々と自身の農地を耕し収穫を続けている。
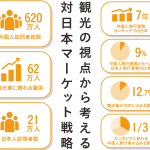
特別レポート(2019/06発刊10号より) 観光の視点から考える対日本マーケット戦略(1/3) 2000年から現在まで、カンボジア観光客の増加状況 カンボジア首都プノンペンから国道5号線に沿って北西に約300キロメー … [続きを読む]

特別レポート(2018/05発刊8号より) カンボジア農業最前線 〜最貧国の零細国家が手にした『神器と信用』が引き起こす農業変革の波〜(1/4) 高層ビルや高級コンドミニアムが次々と建設され大手小売や飲食チェーンの進出も … [続きを読む]

カンボジア経済データ (2017/12/22更新) 概要 面積 18.1万km2〈日本の2分の1弱〉 標準時 UTC+7〈日本より2時間遅れ〉 人口 15.76百万人(2016年世界銀行) 首都 プノンペン〈人口:183 … [続きを読む]