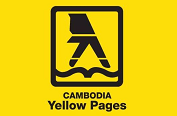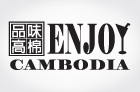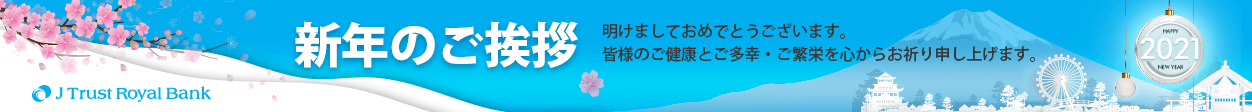

国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の最新報告によれば、2024年の送金額がGDPに占める割合で、カンボジアとフィリピンがASEAN諸国中トップの9%を記録した。この比率は、同年に約29.5億ドルを海外から受け取ったカンボジアにとって、外貨獲得源としての出稼ぎ労働者の重要性を再認識させるものである。
カンボジア政府は労働者の合法的海外就労を推進しているが、ESCAPは「資金不足から、依然として多くの労働者が非正規ルートでタイへ渡航している」と指摘した。一方、2024年には1.38百万人のカンボジア人が海外で働いており、そのうちタイが最大の就労先である。また、女性労働者の割合は5割を超え、家事労働、製造業、介護・エンターテインメント分野での需要増加を背景に、今後もこの傾向は続くと予想されている。
送金コストの構造にも注目が集まる。ESCAPの分析では、タイ発の送金については、為替マージンよりも手数料の比重が高く、銀行送金では手数料が最大16.3%にも達する。一方、送金業者を使えば3.9%に抑えられるケースもあるが、それでも国際標準の持続可能な送金コスト水準(3%以下)を上回っている。
こうした中、SPTF東南アジア金融包摂支援プログラムのディレクター、ニティン・マダン氏は「送金する側と受け取る家族の双方に、金融とデジタルのリテラシー教育を施すべきだ」と述べた。背景には、詐欺リスクや過剰手数料といったトラブルが多発している現状がある。
送金額は前年の29.4億ドルからわずかに増加したが、働く側の所得格差は顕著である。例えば、タイやマレーシアで働くカンボジア人の平均月収は約400ドルにとどまる一方、韓国や日本での労働者は1500ドル近くを得ている。
ESCAP報告は、送金が家計支援とマクロ経済の安定維持に貢献していると評価する一方、カンボジアのような「高送金依存型経済」に対し、国内雇用創出の強化や移民政策の持続的改善を求めている。
なお、国際比較においては、中央アジア諸国のタジキスタン(48%)やトンガ(41%)などが際立って高い比率を示しており、カンボジアの9%は依然として「中程度以上の依存度」と位置付けられる。
また、本記事で取り上げられた政府統計には、非正規移民や地下送金(インフォーマルチャネル)の影響が反映されていない可能性がある点にも留意すべきである。