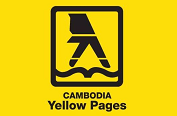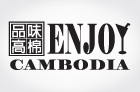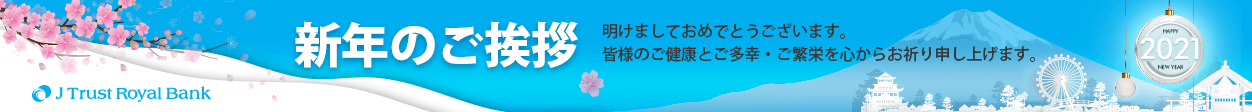

2012年4月に産声をあげたカンボジア証券市場。その後5年半が経過した現在、上場企業数はたったの5社。株式取引が成立しない日もあるほど市場には閑古鳥が鳴いている。 2006年から2007年にかけて大いに盛り上がった隣国ベトナム証券市場の「2匹目のドジョウ」にはなれなかったカンボジア市場。その要因は何か、そして今後活性化する可能性は?
ASEAN後発新興国であるカンボジア、ラオス、ミャンマーの証券取引市場はこれまで述べた通り、まだ産声をあげたばかりの黎明期から抜け出せずにいる。これは各国の証券取引インフラの未整備や発信力の弱さなど各国取引所運営の巧拙に当然その原因の一端はある一方、2008年のリーマンショック以降の各先進国の金融緩和対策から最近の引き締めへの流れなどから、世界の投資・投機マネーがわざわざ新興国の極小マーケットにまで向かわなくなったという世界的な潮流の影響も無視できない。
リーマンショックが起こる前の2006年〜2007年のプチバブルをきっかけに大きく飛躍できたベトナム市場との単純比較はこの点において難しい。取引所の実態とは乖離した投資・投機マネーフローのロジックから見ればその流れは逆流ではあるが、そもそもの取引所の真の実態というべき、その取引所に株式を上場している上場企業各社の実力を眺めていると、筆者はそこに希望を見出せる。
 CSXに上場している5社は、各々まだ企業規模としては小粒ではあるが、業績は極めて堅調で国家経済の成長とともに確実に成長を描ける企業ばかりだ。人口増加が確実なカンボジア首都プノンペンでは水道利用は確実に増加し、PPWSAは引き続き上水道事業を拡大していくだろう。プノンペンとシアヌークビルの各港湾も今後の経済成長の過程で確実に増えて行く物流量の恩恵を十分に享受していくはずだ。老舗縫製業の台湾系GTIも人件費の高騰という逆風の中で堅実に業績を伸ばしており、PPSEZに進出している多くの日系工場も同じく人件費高騰に悩まされつつ投資拡大意欲に衰えを見せていない。
CSXに上場している5社は、各々まだ企業規模としては小粒ではあるが、業績は極めて堅調で国家経済の成長とともに確実に成長を描ける企業ばかりだ。人口増加が確実なカンボジア首都プノンペンでは水道利用は確実に増加し、PPWSAは引き続き上水道事業を拡大していくだろう。プノンペンとシアヌークビルの各港湾も今後の経済成長の過程で確実に増えて行く物流量の恩恵を十分に享受していくはずだ。老舗縫製業の台湾系GTIも人件費の高騰という逆風の中で堅実に業績を伸ばしており、PPSEZに進出している多くの日系工場も同じく人件費高騰に悩まされつつ投資拡大意欲に衰えを見せていない。
日本に新興株式市場が生まれIPOブームが再発した時代、筆者もその渦中にいたが、そこで見たものはIPOによって売り抜けを狙う、会社の体裁だけを繕い上場していくダミー会社ともいうべき数多くの企業群であり、中には詐欺事件に発展したものもあった。それから比べればCSXに上場している中堅企業群は、派手さはないものの地に足を着けて堅実に実業を営む事業会社ばかりである。
投資・投機マネーの流入よる実態と大きく乖離した膨張は当面見られないであろうが、長期的にみれば上場企業群の堅実な成長にあわせて市場も着実に成長していくはずだ。
CSXは今後どのような成長を遂げていくのか。株式市場の将来を予想するのは不可能だが、一つの参考指標としてはその国のGDPと株式市場の時価総額(上場している企業の価値の合計)を対比する考え方がある。絶対的な基準はないが、株式市場時価総額がGDPの1.5倍を超えてくると市場は過熱気味、つまりバブルに突入しているという見方がある。例えば日本は1990年代に株式時価総額がGDPの1.5倍近くに達した後に崩壊、その後60%~80%のレンジで推移した。10月30日現在、ベトナムの株式市場時価総額の合計は約1,200兆ドン。ベトナムのGDPは2016年で約2,019億米ドル(約23兆円)であり、ベトナム株式市場はまだGDPの25%にも達していない。カンボジアのGDPは2015年推計で約177億米ドル。CSX上場企業の本年9月末現在の時価総額合計は約3億ドル、GDPのわずか1.7%である。
またベトナム市場が2006年に一気に活性化する起爆剤となったのは、現地大手乳製品メーカーを始めとした現地有名企業の上場にあった。カンボジアの企業がCSXに上場するメリットを感じることができず、様子見している現状において、有名もしくは話題性ある現地企業をいかにIPOに導くか、市場関係者による地道な啓蒙・誘致活動が欠かせないことは言うまでもない。
長く黎明期が続くCSXではあるが、国家経済が堅調な成長を続ける可能性が高いカンボジアにおいてその潜在成長可能性があることは間違いない。バブル的な短期の値上がりを期待するのではなく、カンボジアの経済成長とじっくり長く付き合う意識でCSXと向き合う投資家が増えていくことに期待したい。
昨今その存在意義そのものが厳しく問われている日本の農協は、戦前から戦後、そして高度経済成長時代、日本の農業発展に大きく貢献した農業組織でした。GDPの3割を占めるカンボジア農業の現況は、まさに農協を必要としていた当時の日本の農業の姿と重なります。
JCGroupは2008年創業以来の主要事業であるカンボジア農業に日本の知見・ノウハウを導入、「古き良き日本型農協」の機能をカンボジアに実現させ「Made by JC(Japan & Cambodia)」によるカンボジア農業の産業化に貢献することを目指しています。
http://jcgroup.asia/
早稲田大学政経学部経済学科を卒業後、日本の大手監査法人、戦略コンサルティング兼ベンチャーキャピタル(一部上場企業 執行役員)を経て、2008年カンボジアにて「JCグループ」を創業。日本公認会計士・米国ワシントン州公認会計士。